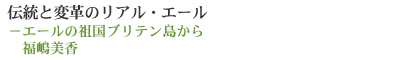
ブリティッシュ・エール その起こりと歴史
ここでブリテンのエールの歴史をおおまかにたどってみよう。
古代ブリテンでは、古代ローマ帝国に支配される前、蜂蜜を発酵させたミードと呼ばれる蜜酒造りが盛んだった。やがて人口増加とともに集落が増えて蜂蜜採取が難しくなると、蜂蜜は貴重な甘味料となり、ミードは高級酒として好まれた。一方、庶民向けに蜂蜜の代用品として糖分を含む発芽した穀物が使われるようになり、品質改良が繰り返された。これが安価であまりにも一般に出回ったため、高級な元祖ミードと区別する必要がでてきた。そこで穀物からできた酒の呼び名としてエールという言葉が生まれたといわれる。
かつてローマ人がブリテンに上陸したとき、彼らはブリテンにワインをもたらしたが、当時はワインこそ高級であり、穀物酒は下等と見なされていた。6世紀後半に、アウグスチヌスを長とするベネディクト派の修道僧が、ローマ教皇の命を受けてキリスト教布教のためにブリテンに上陸する。これを機にブリテンも急速にキリスト教化することになるが、このころのローマの修道僧が、ブドウが収穫できない北ヨーロッパで、ワインのかわりに穀物酒つまりビールを修道院で造り始めたのがことのおこりだ。
8世紀になるとキリスト教会はさらに大きな力を持つようになる。人々が福音を求めて教会や修道院に日常的に訪れ、修道院で醸造されていたエールは、人々のための飲料あるいはパンに添えるスープとしてもてなされるようになった。修道院の周りには、巡礼者を迎え入れるエール・ハウス、タヴァーン、インなどが姿を現すようになる。
12世紀以降は聖トマス・ベケットの殉教地カンタベリーを最大の巡礼地として、教会の近くには巡礼者に飲食物と宿泊を提供するホスピスも設けられるようになり、14世紀には、商業目的で酒を販売するところに看板の設置が義務付けられ、今に知られるパブのサインの由来ともなった。
また、イギリスでは長らくグルートと呼ばれるハーブがビールの味付けに使われていたが、15〜16世紀にかけて、フランダースからもたらされたホップが、そのさわやかな苦味と抗菌作用により市民権を得始めて、16世紀からがケント地方で入植者たちにより本格的に栽培されるようになる。そして17世紀後半にはグルートはほぼ姿を消し、ホップが全面的に使われるようになった。
古典的エールを守ろう!CAMRAの発祥
 18世紀前半、ロンドンを中心に黒ビールのポーターやスタウトが流行する。産業革命の只中、19世紀半ばから人々がガラスコップでビールを飲むようになると、味に加えて色彩も重視されるようになった。チェコで淡色のピルスナーが開発されたのも同じころである。19世紀後半にはバーミンガムに近いバートン・アポン・トレントで生まれたペール・エール(ポーターやスタウトに比べて淡色のエール)が1世を風靡する。 18世紀前半、ロンドンを中心に黒ビールのポーターやスタウトが流行する。産業革命の只中、19世紀半ばから人々がガラスコップでビールを飲むようになると、味に加えて色彩も重視されるようになった。チェコで淡色のピルスナーが開発されたのも同じころである。19世紀後半にはバーミンガムに近いバートン・アポン・トレントで生まれたペール・エール(ポーターやスタウトに比べて淡色のエール)が1世を風靡する。
このころビール醸造の技術開発がすすみ、低温殺菌法、冷凍機、カーボネーション技術(注)、ビールろ過機などの発明が相次いだ。だがこれらの新技術を活用するには、伝統的な木樽が不都合だったため、かわりに金属製樽(ケッグ)の開発が進み、ビール造りは急速に合理化へと向かっていく。
第2次世界大戦後、この傾向はいっそう顕著になり、大手醸造メーカーの近代的手法によるエール醸造が市場を独占するようになった。この波を受けて伝統的な手作りかつ樽熟成によるエールが、パブから消滅する危機に瀕した。
こうした状況を憂い、大企業による合理化の流れに歯止めをかけようとしたのがCAMRAだ。一部の古典的エールを愛好するジャーナリストたちがロンドンのフリート・ストリートを拠点に「古典的エールを守ろう」と呼びかけ始めたのが、そもそものおこりである。
 彼らの呼びかけは、やがて多くの消費者の支持を得、大規模な消費者運動へと発展し、20世紀でもっとも成功した消費者運動のひとつとしても知られるようになった。 彼らの呼びかけは、やがて多くの消費者の支持を得、大規模な消費者運動へと発展し、20世紀でもっとも成功した消費者運動のひとつとしても知られるようになった。
名実ともに戦後の「リアル・エール・リバイバル」の立役者、それがCAMRAである。それまでビール醸造は大手メーカーに独占され、新たに醸造所がつくられることは稀だったが、CAMRAの活発な呼びかけが功を奏し、その後300以上の新たなリアル・エール醸造所が誕生している。
CAMRAの主なねらいは、消費者の権利を守り、品質と価格価値の向上をうながすこと、人々の生活に密着するコミュニティ・パブと伝統的なビール、サイダー(りんご酒)やペリー(なし酒)などを、国の-歴史文化遺産として保護すること、そしてビール産業全体の発展と改善を図ることにある。
今日、オフィシャルグッズや出版物の販売、イベントの興業を主な収入源として運営され、GBBFをはじめとする各種イベントの企画運営、ビール関連の出版物発行、リサーチ、品質チェックなどを通してビールとパブ業界の発展に貢献しており、こうした活動はヨーロッパ諸国の関連機関団体にも影響を与えている。 |



