|
|
|


■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
 |
|
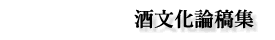
|
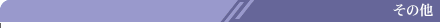 |
 |

はじめに
清酒に関する歴史研究は少なくないが、酒造りに較べると流通についてはそれほど分厚い蓄積があるわけではない。流通面が考察されていても、ある酒造家の販売市場の変遷などが論じられることが多い様である。また、酒造会社の会社史においても、製造面に比して割かれる頁数はさほど多くない。こうした研究上の偏りについては、酒造家に旧家が多いため、史料が比較的残りやすいという事情も考慮しなければならないが、他方、他分野における通弊と同様に、研究関心の生産部分への偏重が作用しているのであろう。
本稿では、昭和初年における清酒流通について論ずることにしたい。この頃、第一次世界大戦にともなう空前の好景気の後を受け、度重なる恐慌に加えて関東大震災という未曾有の自然災害に見まわれたことで、日本経済は長きにわたり呻吟(しんぎん)を続けることになった。その中で、清酒をめぐっても、生産者、商人を問わずその経営は振るわず、乱売問題などを抱える業界は再編を迫られていた。
そうした中、清酒流通に三井物産株式会社が参入を試みた。もう少し具体的に述べると、灘魚崎郷の松尾仁兵衛商店が醸造する「金正宗」という銘酒を一手販売することで、清酒業界への新規参入に挑んだのであった。詳細は後述するが、三井物産とは言うまでもなく、戦前戦後を通じて、わが国を代表した貿易商社である。後年人口に膾炙(かいしゃ)することとなった表現を借りるならば、あらゆる種類の商品を地球上のいかなる地域とでも取引する、いわゆる「総合商社」である。そのような巨大商社が、なぜこの時期に清酒界とのかかわりを持とうと考えたのか、その一端を明らかにすることにしたい。
三井物産−巨大商社−
まずは、同社の成り立ちについて簡単に紹介しておくことにしよう。その設立は明治9(1867)年のことであった。当時の三井家の事業としては、明治に入って開始した銀行業と江戸時代以来の長い歴史をもつ呉服販売業、そして幕末以降携わってきた諸国物産の売り捌きなどが主たるものであった。三井物産が誕生するに至ったのは、政府の有力者である井上馨が一時下野していた間に立ち上げていた先収会社という商事会社を、同人が政府復帰を果す際に引き継いだことによる。
清酒とのかかわりは呉服店において見出すことができる。三井家の祖業である呉服業に関しては、銀行業に差し障りが出るのを防ぐため、「三越得右衛門」という別の家を擬制的に設立し、一応分離していた。この呉服店においては、このようにやや自由度が高まったことと、さらに明治初年の旧来の株仲間制度の廃止の影響もあってか、その大阪店では西宮において明治5(1872)年から酒造を行っている。勿論、西宮に移住して酒造りを営んだ訳ではなく、大阪に本拠を置きつつ酒造経営に携わっていたのであるから、これはいわゆる「出造り」である *1) 。こうした酒造りだけでなく、同年には東京において下り酒問屋の一員として丸越印で清酒の卸売業も始めている。このように、清酒については生産・流通と二本立てで関与していたわけである。しかし、西宮における酒造業の方は余りうまくいかなかった様で、早くも明治9年には廃業を余儀なくされている *2) 。酒問屋については一定の成果をあげることに成功しており、旧来からの同業者に混じり中位ぐらいに位置していた *3) 。だが、こちらの方も好調は長続きせず、明治22年にいたり撤退に追い込まれている *4) 。その後の清酒業界との関わりの点では、管見(かんけん)のかぎりでは、明治後期から大正期においてその形跡は殆ど無かったと見られる *5) 。
話を三井物産へ戻そう。設立当初の事業としては御用商売が中心であった。政府米や官営三池炭坑の石炭などについて、明治政府と一手販売契約を結び、ロンドンやパリなどに支店を出してその売り捌きを担当した。その後、明治10年代後半以降、綿糸紡績業が目覚ましい発展を遂げる中、紡績機械や原料綿花の輸入を主導して御用商売からの脱却を図った。また、日清戦争を経て、さらに取扱商品の多様化が進んでいった。他にも、戦前期日本にとって最も重要な輸出品であった生糸輸出でも頭角を現わした。
幕末開港以後の日本の貿易形態を考えると、本来、日本にとって貿易の利益は国益上はずせないが、実態としては資本・情報の面で勝る外国人商人が商権を握っていた。そのため、日本人商人はせいぜい国内居留地に拠点を構える外商相手に取引を行う程度に止まっていた。これら乗り越えるべき外商たちと対峙しつつあったのが、三井物産を初めとする直輸商社であった。後年にいたり国力の増進にともなって両者の力関係にも変化が生じ、明治末〜大正初めにおいてようやく内商取扱高が貿易高の過半を占めるに至った。一応、念願の商権自立が達成されたのである。同じ頃、三井物産は先述の如く「総合商社」化した。同社自身の表現によれば「問屋的百貨業」ということになる *6) 。多種多様な商品を大量に扱った同社の取引高は、戦前においては圧倒的な比重を占め、ほぼ一貫して首位に座り続けた。幹部をして「三井ハ常ニ老懶(ろうらん)ノ風アリトカ不親切ナリトノ世評ヲ耳ニスル」と言わしめる様な、殿様商売的な面もあったようである *7) 。
その頃の経営内容を見ると、第一次大戦中には機械輸入を大いに伸ばし、さらなる成長を実現した。しかしながら、空前の好景気に浮かれることなく、比較的着実な経営を堅持した。この点で、盛んに投機取引を行い、一時は取引高で三井物産を凌駕した鈴木商店が、その放漫経営がたたり昭和2(1927)年に破綻に追い込まれたのとは大きく異なると言える。しかしながら、極度の不況の影響は同社といえどもまぬがれることは難しく、業績は頭打ちとなり閉塞感が漂った。その打開に踏み出したのが、当時三井物産筆頭常務であった安川雄之助であった。三井物産の清酒流通参入は彼が打ち出した経営方針の影響が強く見られるのである。
|
|
|
 |
本サイトの画像及び文章その他一切のデータの無断使用・転載を禁じます。
copyright(c)1997-2004 Sakebunka Institute,Inc all rights reserved |

