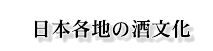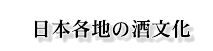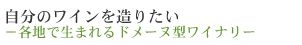
近年、ぶどう畑を併設した本格的なワイナリーの創業が目立っている。酒造免許の取得が困難であること、国内の酒類の消費が飽和していること、流通の規制緩和などで価格競争が激しさを増していることなど、酒造業の創業は容易ではない。にもかかわらずワイナリーが相次いで誕生するのはなぜか。本稿は特に個人による創業に焦点を合わせ、その背景と可能性を考える。
手触りの酒作り |
|
 「引退したら作りたい酒だけを、年に300石くらい作って生活したいね。それくらいなら売るのも作るのもひとりでできる。なんといっても楽しいから……」
「引退したら作りたい酒だけを、年に300石くらい作って生活したいね。それくらいなら売るのも作るのもひとりでできる。なんといっても楽しいから……」
以前、ある清酒メーカーの製造技術者が何気なく口にした言葉だ。こうした思いが実現できれば、量産・量販のシステムが中心の現在の酒造業が少し変わるように思う。品質レベルが高いだけでなく個性や主張があり、わかってくれる人にだけ飲んでもらえればいい。
飲み手と作り手の距離は近く、お互いの手触りを確かめながら酒を楽しむ。そんなあり方が酒にはもっとあってよい。
酒類製造免許というハードル |
|
いま、日本で酒造業への新規参入は簡単ではない。そこには規制・市場・ビジネスの仕組みなど、さまざまなハードルがある。
まず、酒類製造免許について。これは、人的要件、経営・製造能力の要件、需給調整上の要件などを満たさなければ免許されない。
人的要件は、過去の違法行為の有無などいくつかの免許されない事項が具体的に示されている。
経営・製造能力の要件では、酒類の製造に必要な知識や技術の習得レベルや、資金的な裏づけの有無などがチェックされる。
需給調整上の要件は、酒税保全の観点から需給の均衡を乱すと考えられる場合に税務署長の判断で拒否できるというもの。需給状況の現状から、清酒、焼酎、合成清酒、みりんは、既存の免許業者が経営の合理化などのために新規に免許を要する場合を除いて原則免許されない。
さらに、これらの前提として、年間製造数量の下限が酒類ごとに定められている。清酒・焼酎甲類・合成清酒は60KL、焼酎乙類は10KL、ビールは60KL、果実酒・ウイスキー類・リキュール・雑酒は6KLである。よく知られるように数年前に地ビールメーカーが多数誕生したのは、この製造数量の下限が引き下げられたからだ。
ワイナリー新設ラッシュ |
|
酒類製造が免許されたとしても、創業には一般のビジネスと同じく、何を作り、どこで、どのように、いくらで販売すれば、消費者に買ってもらえるかを構想し、実現するという課題がある。基本的に国内の酒類消費は飽和しており、既存の有力なメーカーが消費者の支持を得ようとしのぎを削っている。市場を細分化し、小規模での参入であれば隙間市場を狙わざるを得ず、大規模な参入ならば量販・量産で優位に立つ仕組みが要る。いずれも簡単ではない。
しかしながらこの10年間に20を超えるワイナリーが新たに誕生した。そしてほとんどが、ぶどう畑を併設した本格的なものという(『酒販ニュース』2002年5月21日号)。経営主体は大きく四つ。ひとつは酒類メーカーの事業多角化の一環というもの。ふたつめは地場産業の振興のために行政主導の第三セクターで運営するというもの。三つめは外食業者などサービス業がワイン作りに取り組むというもので、農業テーマパークに併設されるケースもある。四つめはワインメーカーに勤務していた個人が独立して開業する、というものだ。
今回、焦点を合わせるのは四つめの個人によるワイナリー創業である。彼らはメーカーに勤務したままワイン作りにかかわることができた。にもかかわらずあえてリスクを背負って独立するのは、何を求めたのであろうか。
そして、そのビジネスとしての基盤はどのように形づくられたのであろうか。
|