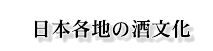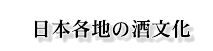|
|
|


■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■ |
|
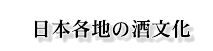 |
 |
 |

北海道の酒から小樽の酒へ北の誉
 翌日、小樽の北の誉を訪ねました。二階に事務所をおく「酒泉館」は、一般のお客様が立ち寄れる資料館として平成八年の工場改修の際に設けられました。吹き抜けのある気持ちのよい展示室には創業当時からの同社の足跡だけでなく、製品の検査をおこなう試験室の様子が公開されています。製造現場は「酒泉館」から見えませんが、酒づくり期間中(一〇月から三月頃まで)は工場見学を受け入れます。 翌日、小樽の北の誉を訪ねました。二階に事務所をおく「酒泉館」は、一般のお客様が立ち寄れる資料館として平成八年の工場改修の際に設けられました。吹き抜けのある気持ちのよい展示室には創業当時からの同社の足跡だけでなく、製品の検査をおこなう試験室の様子が公開されています。製造現場は「酒泉館」から見えませんが、酒づくり期間中(一〇月から三月頃まで)は工場見学を受け入れます。
小樽は江戸後期から漁業の町として発展しました。安永年間(一七七二〜一七八〇)に弘前・江差から小樽に鰊の漁場が移り、北前船による海運の拠点となったのです。そして、明治維新後は北海道の玄関として隆盛を極めます。明治一三年に開通した小樽〜札幌間の鉄道は日本で三番目に早いもので、幌内に発見された石炭を本州に送り出すために突貫工事でつくられました。明治二六年には日本銀行の派出所が置かれ、明治三二年には国際貿易港に指定されます。
しかし、その後、国際港としての役割を終え、北海道経済の中心としての地位を札幌に譲ると徐々に衰退していきます。漁業も明治二〇年代をピークに鰊の漁獲量が激減し、昭和三〇年代以降はほとんど水揚げがなくなってしまいました。現在は、煉瓦づくりの倉庫街や金融機関の重厚な旧本社屋が残る趣のある街として、あるいは鮨や魚介類のおいしい街として、年間八〇〇万人が訪れる観光都市となっています。
北の誉が「酒泉館」をもったのは、こうした街の変化や、日本国内での北海道のポジションが変化していることと無関係ではありません。
開発とともに成長
 北の誉を創業した野口吉次郎氏は金沢の出身で、明治一九年に「小樽がいい」と聞いて北海道に渡りました。行商や日雇いで生計を立てながら、小樽で醤油の製造を引き受ける機会を得て、明治二三年にそれを一手に販売する丸ヨ野口商店を設立しました。当時、北海道の人口は五〇万人足らずでしたが、その後の一〇年間に倍増します。食事に欠かせない醤油はまさに飛ぶように売れたことでしょう。そうしてひと財産つくった吉次郎氏は、明治三四年に酒造業に参入します。北の誉の創業です。奇しくもこの年は、北海道の人口が一〇〇万人を超えた記念の年でした。 北の誉を創業した野口吉次郎氏は金沢の出身で、明治一九年に「小樽がいい」と聞いて北海道に渡りました。行商や日雇いで生計を立てながら、小樽で醤油の製造を引き受ける機会を得て、明治二三年にそれを一手に販売する丸ヨ野口商店を設立しました。当時、北海道の人口は五〇万人足らずでしたが、その後の一〇年間に倍増します。食事に欠かせない醤油はまさに飛ぶように売れたことでしょう。そうしてひと財産つくった吉次郎氏は、明治三四年に酒造業に参入します。北の誉の創業です。奇しくもこの年は、北海道の人口が一〇〇万人を超えた記念の年でした。
その後、北の誉は矢継ぎ早に旭川や札幌に進出、戦中の企業整備や戦後の混乱を生き抜き、同社は北海道を代表する酒として躍進します。昭和四二年には東京に営業拠点を置いて全国市場に進出、昭和四七年ごろには約一〇万石の清酒を製造し量的にはピークを迎えます。ちょうど同じころ、北海道は戦後力を注いだ水田の開発が結実し、米の生産量で全国トップになります。北海道の本格的な開拓が始まってからほぼ一世紀、これは画期的なできごとでした。そして、北の誉は、北海道の開発と常に軌を同じくしていたと思わずにいられません。
酒造業のソフト化
 同社の野口禮二社長は、「これからは小樽の酒としての立場を明確に打ち出す」と言います。昭和四〇年代に灘・伏見の酒とも伍す北海道の雄として全国展開した北の誉は、その後イメージの曖昧さに苦悩しました。一〇万石という今ならトップ一〇に入る製造量を達成したために、消費者やマスコミが北の誉を地方のナショナルブランドとして扱いはじめたのです。希少性も地方色も打ち出しにくい状況は、その後の清酒の長期低迷の影響をもろに被ることになりました。需要減とより規模の大きなメーカーとの激しい競合で、現在の製造石数はピーク時の一〇分の一にまで縮小してしまったのです。北海道の大規模清酒メーカーはどこも似た状況に陥り、かつて北海道の四割を占めていた道産の酒のシェアは二割に半減しています。 同社の野口禮二社長は、「これからは小樽の酒としての立場を明確に打ち出す」と言います。昭和四〇年代に灘・伏見の酒とも伍す北海道の雄として全国展開した北の誉は、その後イメージの曖昧さに苦悩しました。一〇万石という今ならトップ一〇に入る製造量を達成したために、消費者やマスコミが北の誉を地方のナショナルブランドとして扱いはじめたのです。希少性も地方色も打ち出しにくい状況は、その後の清酒の長期低迷の影響をもろに被ることになりました。需要減とより規模の大きなメーカーとの激しい競合で、現在の製造石数はピーク時の一〇分の一にまで縮小してしまったのです。北海道の大規模清酒メーカーはどこも似た状況に陥り、かつて北海道の四割を占めていた道産の酒のシェアは二割に半減しています。
「身の丈に合った均衡点をつくり回復に向かわせるタイミングが近いと思います。すでに製造量の過半数が純米酒や吟醸酒になりました。これからは価格競争と一線を画して、高価ではないけれども付加価値の高い酒を開発していこうと考えています。
情報の発信装置として小樽はすごい力を秘めています。これも活用したい。『雪あかりの道(二月)』と『潮祭(七月)』の二つの大イベントを中心に年間八〇〇万人が来て、おいしい食事を楽しんでいるのですから、小樽の楽しい思い出を北の誉に付加することが狙えると思います。さらに余市のウイスキーやワイン、札幌のビールなども連動させて、小樽を中心に良質な酒があるイメージもつくって行きたいですね」
野口社長が語る北の誉の将来像は、やはり観光などソフトな経済に基盤を移そうとする北海道の姿も重なるように思いました。
|
|

|
本サイトの画像及び文章その他一切のデータの無断使用・転載を禁じます。
copyright(c)1997-2004 Sakebunka Institute,Inc all rights reserved |