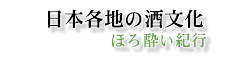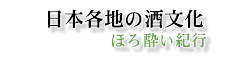|
|
|


■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■ |
|
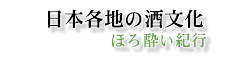 |
 |
 |
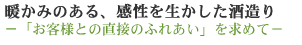
木々と水が育んだ酒 |
|
 というわけだから、「澤乃井」という名称にどういう由来があり、いつから使われていたのかといった基本的なことも、まったくわかっていないらしい。
というわけだから、「澤乃井」という名称にどういう由来があり、いつから使われていたのかといった基本的なことも、まったくわかっていないらしい。
「たぶん『沢井』という地名が先にあって、あとは地名のあいだに『乃』を入れただけでしょう。そうなると、あんまりおもしろくない話ですけど(笑)。でも沢井という地名は、近くに沢がたくさんあって、いい水がたくさんあるから井戸がいらないというので、『井』の上に『沢』がついたということのようです」(山崎副社長)
同社の敷地内には、170年以上前に掘られたという横井戸がある。この洞窟からは現在も豊かな水があふれ、仕込み水として使われており、水が豊富なことは確かだ。
さて昭和40年代まで、「澤乃井」の消費地はほとんど西多摩に限られていた。ただ、なぜかそれ以前から、東京江東区の深川周辺にはこの酒を扱う店がいくつかあったらしい。このおよそ60キロメートルの距離を越える鍵は、どうやら小澤家のもう一つの仕事、林業にありそうだ。
かつて奥多摩や青梅から切り出された木材は、駅でいえば沢井から一つ東寄りの軍畑付近で筏に組まれ、多摩川を下っていった。行き着く先は、現在の江東区木場。古くは辰巳芸者で知られた盛り場・深川とは目と鼻の先だ。おそらく、青梅近辺から延々多摩川を下って木場にたどり着いた筏師や、もともと青梅出身で木場あたりに製材所を開いた人びとなどが、故郷の酒を懐かしんで「澤乃井」を求めたのだろう。
話は変わるが、前に述べたように同社はJR沢井駅のまん前にある。これは偶然ではなく、同社がその後に駅を作ったというのが正しい。もともと青梅から奥多摩にいたるこの線は、小澤家など沿線の有力者が資金を出し合って作った、文字通りの「私」鉄だったのだから当たり前だろう。
この旧奥多摩鉄道株式会社は昭和19年、国に買収されて現在の青梅線とつながるわけだが、山崎副社長が入社した昭和27年当時でも、杜氏が小僧を駅まで走らせ、列車を待たせておくなどという豪気なことが行われていたらしいから、その頃までは「わが社の鉄道」という意識が残っていたのかもしれない。
こうした資金力の背景は、酒造りというよりはやはり林業だろう。
まゝごと屋は口コミ戦略の要 |
|
 さて、同社の酒が西多摩地区を出て、都心方面へと進出したのは昭和39年のことである。
さて、同社の酒が西多摩地区を出て、都心方面へと進出したのは昭和39年のことである。
この頃から酒類に対する規制が緩やかになり、同社はこの年、まず縁戚関係にあった板橋区の問屋との取り引きを始め、都心進出への足掛かりとした。
「当時、ちょうどナショナルブランドが育っていくころで、酒質としてはどんどんどんどん甘口になっていった時代ですね。このへんだと『大関』が強かったので、『月桂冠』と『大関』を買ってきて分析して、われわれも一生懸命甘口を追いかけていましたね」(山崎副社長)
だが、新参者が灘、伏見の大手に互して販路を開拓するのは容易なことではない。テレビでスポットCMを流したこともあったが、ナショナルブランドの露出量にかなうはずもなく、同社は別な手立てを考えなければならなかった。
そこで採用されたのが、当時まだどこもやっていなかった蔵見学である。マスコミに頼れないなら、口コミを活用しようというわけで、とにかく「澤乃井」を育んだ奥多摩の自然に触れ、蔵でどんな酒造りをしているのか見てもらおうとしたのだ。
昭和41年、川沿いの澤乃井園でのバーベキューとセットになった蔵見学がスタート。
「最初は、問屋さんに笑われましたね。酒蔵なんてのは、品質の問題もあるし、夏は蔵を開けるもんじゃない。それにまだなんとなく女人禁制みたいなものもありましたし」(山崎副社長)
しかも、こうした反対を押し切って進めたこの「お客様との直接のふれあい」戦略は、なかなか目に見える売上にはつながってこなかった。努力が実を結んだのは10年ほどのち、昭和50年代に入ってからのことである。オイルショック後の日本経済の減速は「ディスカバー・ジャパン」という国内旅行ブームを巻き起こし、豊かな自然の残る奥多摩にも目が向けられはじめたからだ。
そこで同社では、この戦略をさらに推し進めるため、澤乃井園の隣に清酒を飲める飲食店を開くことを計画する。バーベキューでは普通酒ならなんとかいけるものの、当時同社が発売をはじめた特撰酒を飲む場にはならない。そこで、日本酒に合う肴を厳選した店が求められたのだ。
当初、山里の雰囲気を求めて川魚や山菜料理も検討してはみたが、調べてみると地元の既存店で使っているのは他県からの輸入品。結局、「澤乃井」の仕込み水を使った豆腐・湯葉料理をメインにするというコンセプトが固まった。店名は、素人が始めたという意味と、豊かな自然のなかで童心に帰るという意味を込めて「まゝごと屋」。
こうして、今では奥多摩でも指折りの人気店に数えられる料亭がオープンしたのは、昭和54年のことである。しかし、豆腐・湯葉料理というコンセプトは女性向きに見える。事実訪れるのは主婦が多いし、そうなると店で特選酒を味わう客は多くはない。だが、亭主が仕事をしている昼間、自分だけがおいしい料理を食べていることにちょっぴり後ろめたさを感じるのか、帰りには売店で特撰酒を買い求め、亭主への土産にする人も多い。そして、家で飲んで気に入ってもらえればしめたもの。今度は近くの酒販店で、指名買いをしてくれるわけだ。
つまり、いったん主婦を経由するという迂遠な方法だが、この戦略が着実に実を結んで、清酒全体の需要が下降線をたどりはじめた昭和50年代にも、同社は着実に売上を伸ばしていくことができたのだという。
|
|

|
本サイトの画像及び文章その他一切のデータの無断使用・転載を禁じます。
copyright(c)1997-2004 Sakebunka Institute,Inc all rights reserved |