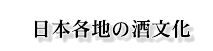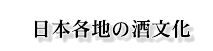|
|
|


■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■ |
|
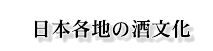 |
 |
 |

やっぱり酒はうまい方がよい |
|
 大正14年に醸造量無制限という破格の免許を受けてから、醸造蔵は神社境内に置かれている。そのため、どぶろく醸造は、当番家から神社へと、場所を移して行なわれるようになった。しかしながら醸造法それ自体は、いまだ従前の形式にとどまっていた。すなわち木製の桶を使用し、麹作りに始まり蔵開きに至るまでの全工程を、どぶろく当番が一貫して管理するというやり方だ。
大正14年に醸造量無制限という破格の免許を受けてから、醸造蔵は神社境内に置かれている。そのため、どぶろく醸造は、当番家から神社へと、場所を移して行なわれるようになった。しかしながら醸造法それ自体は、いまだ従前の形式にとどまっていた。すなわち木製の桶を使用し、麹作りに始まり蔵開きに至るまでの全工程を、どぶろく当番が一貫して管理するというやり方だ。
この醸造法は戦後も続いていたが、温度管理に失敗する例が多く、酸味が強くてとても飲用に供するに価しない、まるで酢みたいな年もしばしばあったという。こうした状況の中から、ついには醸造方法そのものを改善する動きが起こってくる。
昭和52年、税務署の勧めもあって、まず醸造用の桶が木製からステンレス製に取りかえられた。合わせて、老朽化した醸造蔵が、市の補助をえて改修された。醸造法も、酵母を使用した本格的なものへと変化をとげるのである。こうして、その年から、酒造会社によるどぶろく当番への技術指導が本格的に開始されることになった。61年には新たにステンレス製の桶が寄進され、醸造量も従来の350リットルから約450リットルへと大幅に増量されている。
はたして、どぶろくは、酸味のきいた従来のものから辛口のにごり酒へと変化した。どぶろくの味の変化に対しては、氏子たちの間で賛否両論がある。だが、それは彼ら自身が求めた結果でもある。その背後には、氏子自身のどぶろくに対する認識の変化が想定されるのである。
昭和40年以降、新聞(南信日日新聞)紙上では、毎年どぶろくのできぐあいが報じられてきた。また昭和40年代半ばから51年頃にかけては、そのあまりの「まずさ」に、本来なら醸造に関与しないはずの税務署の係官ですら、「せっかく米を使ってつくるなら、もっとしっかりしたものをつくったらどうか」と忠告したというエピソードが残っている。
そうした事情が、氏子たちの醸造に対する認識を変化させたのであろう。当時のどぶろくについて、氏子の一人は、「鼻をつまみ顔をしかめても、神酒だからと思って我慢して飲んだ」と語っている。どぶろくは神に捧げる神酒であると同時に、人の飲用としても供される嗜好品だが、この言葉には、何よりも醸すことそれ自体に意義を求める氏子の認識が、図らずも表現されているといえよう。
にもかかわわらず、昭和52年から醸造法が変化していることを見ると、神酒という従来の価値に加えて新たに味わいという付加価値が、どぶろくに対し求められるようになったと考えられる。そして同じ年の新聞には、ついに「伝統の七色の味復活」といった記事まで登場する。
祭の当日、来賓として臨席した植松杜氏は、昼間のどぶろくに顔を紅潮させながら「あれは、もうどぶろくではない。濁りのある清酒だ」、「昔のどぶろくをつくってほしいと言われても、酒屋がかんでいるからにはとてもできない相談」と満足そうに語っていた。
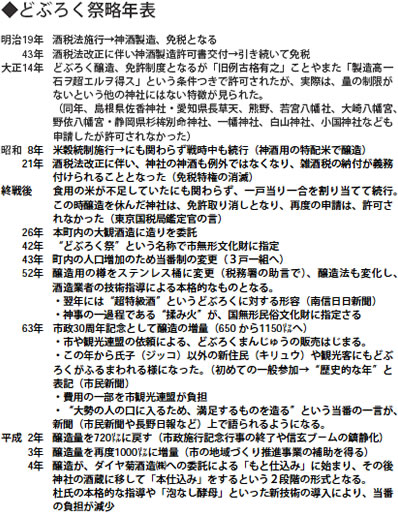
|
お酒の四季報(1997年秋号) |
|

|
本サイトの画像及び文章その他一切のデータの無断使用・転載を禁じます。
copyright(c)1997-2004 Sakebunka Institute,Inc all rights reserved |