|
|
|


■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■
 ■
■
 ■
■
 ■
■
 ■
■
 ■
■
 ■
■
 ■
■
 ■
■
 ■
■
 ■
■
 ■
■
 ■
■
 ■
■

■

■
|
|
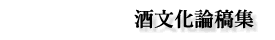
|
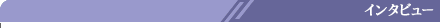 |
 |

|
 |
 マーケティング界の泰斗である石井淳蔵流通科学大学学長が2月に『寄り添う力』(碩学舎)を上梓された。石井氏はブランドマーケティングや営業の特異性にも詳しく、その独自の視点には酒類業界の支持者も多い。今回は新刊の内容や最近の関心事項についてお話をうかがった。 マーケティング界の泰斗である石井淳蔵流通科学大学学長が2月に『寄り添う力』(碩学舎)を上梓された。石井氏はブランドマーケティングや営業の特異性にも詳しく、その独自の視点には酒類業界の支持者も多い。今回は新刊の内容や最近の関心事項についてお話をうかがった。
―― 『寄り添う力』には副題として―マーケティングをプラグマティズムの視点から―とありますが、この本を書かれた思いや、この書名に込めた狙いからお聞かせください。
石井 実は最初に考えていた本の名前は、「それが一体なんぼのもんやねん」でした。関西ではマーケティング学者がいろいろ理屈を重ねても最後にこういう質問が出てくることが少なくありません。つまり有用性を問われるということです。プラグマティズムという考え方は、真理を問うのではなくて、現場・現実から発想して柔軟に考える哲学です。その観点からさまざまな事例を基にマーケティングを考えてみました。しかし本書に取り上げた事例の中から、特にエーザイと徳武産業の話がおもしろいという方が多く、それを端的に表す意味で『寄り添う力』というタイトルにしました。最近は他人を思いやる心が少し弱くなっていると感じていたので、これだと思いました。マーケターの仕事は、相手と同じ目線に立ち、その人のために自分は何ができるのかを考えるところからスタートすると考えています。
■プラグマティズム的な考え方がよいマーケターを育てる
―― 先生がこの本を通じて一番伝えたかったことはどういうことなのでしょうか。
石井 マーケティングの実践は理論を乗り越えて、現実の壁を克服するということです。だからマーケターというものは、ひとつの考え方に拘泥していてはいけない。日々革新が求められので現場で感覚を磨き、その事柄について実践的な理解を深めることが大切なのです。マーケターという仕事は目から鱗が落ちる経験を重ね、これによって、より一段と深い理解を得ることができ、人間としても成長していくことができる仕事だと考えています。
―― なぜそう思われたのでしょうか。
石井 マーケティングを考えるときに市場や現実の理解は不可欠ですが、その理解の仕方にも大きく二つの種類があります。
ひとつは、遠いところから全体を俯瞰的に理解する分析的な「鳥の目の感覚」。そしてもうひとつは、現実に密接してそこでなにが起こっているのかを見極める「虫の目の感覚」。両方ともが大事なのですが、マーケターは「鳥の目」のほうに偏りがちです。
かつては、現場データや分析手法も未進化の段階であったので科学的に進められそうな前者に大きな価値を求めました。しかし、現在ではさまざまなビッグデータや市場調査の結果を使い、消費者ニーズと社会の変化など各種の要素を分析して、洗練された答えを出すことができるようになりました。
たとえば会社の戦略を、昔はマーケターが苦労して考えていたものですが、今ではシンクタンクや広告代理店に依頼すれば、みずからデータを集め解析して3案くらいの回答が手際よく出てきます。ダイエー創業者の中内功氏は、流通を科学的に分析したいと考えて今の流通科学大学を創設されたのですが、そういう意味で、マーケティングは科学に近づいたと言えるのでしょう。そうなると今度はそこから何を選ぶかの選択眼が重要になっています。
■ビジネスインサイトの重要性
―― 選択眼、何が大事かを見極める力ということですね。かなり難しい選択を迫られるのでしょうね。
石井 たとえば、あるジャンルの新商品を開発するとしましょう。市場のニーズを見極め、チャンスのある分野はこれとこれで、そこに到達するための有効なマーケティングチャネルはこれだ、というような戦略はデータを解析するシンクタンクや広告代理店などに頼めば答えを得ることができます。そこから、本当にそれでいけるのかどうかをより精緻に調べようと、さまざまな調査や実験を繰り返せば、より確度を高めることも可能でしょう。しかし、それは無数にいる競合となる相手にも同じことが言えるのです。より精度の高い結果が導き出せたときには、競合にも同じ条件が発生することを意味します。だから最初に考えたときのような肥沃で魅力的な市場ではなく、大激戦市場に変わってしまうかもしれません。まだどこが魅力的なのかが明確にわからない段階ではあるが、どうも大きな市場がありそうだと判断できる力、ひらめきのようなものかもしれませんが、これをビジネスの世界では「ビジネスインサイト」と呼びます。この力が成功する上では大切になります。
―― ビジネスインサイトに強くなるにはどうしたらよいでしょうか。本の最初に出てくる癌患者さんの話の意味も、最初はよくわかりませんでした。
石井 エーザイの理念である「患者様と喜怒哀楽を共にすること」の説明の例として紹介しました。進行癌の患者で疼痛が我慢できないおばあさんが苦しくて毎晩のようにナースコールを鳴らして死ぬ不安を訴えるという話です。ある若い看護師さんが、黙って足を洗ってあげたのです。翌朝、その患者さんから「もう死ぬ死ぬって言わないから」と感謝されます。この行為に医療として科学的に意味があるのかどうかはわからない。しかし、この看護師さんは相手の苦しい気持ちに寄り添い、どうしたら応えてあげられるかを考えて、とっさに足を洗ってあげたのでしょう。同じ現場に何回も出くわしたベテランのスタッフの誰も思いもしない行動です。このような相手に寄り添い意味ある対応するその力が、私はたいへん重要と考えます。『寄り添う力』という本書の題名は、そこから出てきました。
―― 他にもたくさんの事例が紹介されていますが、どれもそのようなヒントがありますね。
石井 現場では、当初予想もできない、いろいろなことが起きているからです。そしてその解決のために日々いろいろな実践がおこなわれる。しかし、そのことが持つ意味は案外現場では意識されていない。そういうときに私のような研究者というものが見ると、そこにいろいろな発見がある。マーケティングの常識を覆すような成功例が世の中にはたくさんあるのです。長野県のヴィラデストファームという新興ワイナリーが成功している話は、オーナーと働く人とお客さんとが互いに共感を軸に結びつく話です。人に寄り添い、共感し合いながら、ビジネスが成り立っていくのです。
四国の靴会社徳武産業もそういう事例です。足のサイズは左右で少し違う場合があるということに気がついて、シューズを片方だけでも販売するという会社です。きっかけは、高齢者用に転びにくい室内シューズをつくってほしいというオーダーにあります。転びにくい靴はできあがり、販売するのですが思うように売れません。あるとき、介護施設で長年寝たきりのおばあさんが同社のピンクの靴を買うのですが、施設の方から押し売りしているのではないかと問い合わせが入ります。急いでその方のところに駆けつけてみると、おばあさんは「かわいいピンクの靴をもう一度履きたい」と思って買ってくださったのでした。そして、しばらくした後におばあさんがその靴を履いて歩けるようになったと連絡が入ります。かわいい靴を履きたい、という思いがリハビリの力になったのかもしれません。この後、一人ずつが持っているニーズになるべく応えようと、片足ずつの注文からさらに仕様を相手にあわせてカスタマイズするシューズ、ネーム入りシューズなどのビジネスへと発展していくのです。
そんなある日、同社を車いすに乗った少年と母親が訪ねてきます。その少年は、長く車いすに乗っているのでシューズを履くことはありません。そのとき社長が「シューズを履きたくないか」と尋ねると、少年は「履きたい」と答え、彼のサイズに合わせたシューズをつくりました。久しぶりにシューズを履いた少年は大変喜び、付き添っていた母親も喜んで泣き出したという話です。一番身近で接している母親ですら気がつかなかった少年のシューズを履きたいという欲求にどうして社長は気がついたのかと言えば、彼はさまざまな経験の中で「人がシューズを履くことの喜び」を知っていて、普通の人にとっては、歩くために履くものでしかないシューズにそれ以外の意味や価値がある、ということを理論あるいは見識として身に付けていたからです。
―― すごいお話ですね。普通に考えたら足の不自由な少年にシューズを履きたいかと質問すること自体、怖くてできません。そう質問できる社長の持つ見識はまさに、真のマーケターの発言ですね。
|
|
|
|
 |
本サイトの画像及び文章その他一切のデータの無断使用・転載を禁じます。
copyright(c)1997-2004 Sakebunka Institute,Inc all rights reserved |

